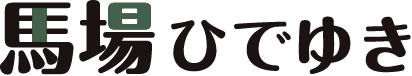3月22日に馬場県議の支援者Tさんの紹介で「第2回えちご上越能」に行ってきました。ステージには鏡板が設置され、さながら本物の能舞台のよう。家の事情で少し遅れてしまい、Tさんの仕舞を見ることができなかったのは残念でした。
次に狂言の「素襖落」は人間国宝の山本東次郎さんが主役(太郎冠者)をつとめました。私の席は後方でしたが、朗々とした素晴らしい声で感激しました。パンフレットをみたら、なんと1937年生まれ今年88歳。能は体幹がしっかりしていないといけないし、発生も腹式呼吸。そう簡単にできるものではありません。酔っぱらいの役ですが軸がぶれずに泥酔状態を見事に演じられて見事でした。
最後は「能」。題材は春にちなんだものでした。平家物語を題材にしたと言われている「熊野」。平宗盛という男に翻弄される妾の熊野。熊野は余命わずかな母親の元に帰省したいと申し出るけれど宗盛はそれを許さず花見に連れていく。途中雨が降って桜が散ったのを見た熊野が母を想う歌を詠んだところ、やっと宗盛の心に届き帰省できるというストーリー。途中華やかな牛車が登場してくるのですが、それが花見の華やかさの演出であり、この演目の醍醐味のようです。
能はとてもスローテンポで進みます。言葉も「候へ」などという古い言葉なので詞章をみなければ理解できません。また当然ですが能面なので表情はありませんから感情は読み取れません。しかし不思議なことにその声や所作からその憂いを帯びた感情がふわぁ〜っと伝わってくるのです。「余情」ってこういうことを指すのかな…と思いながら見入ってしまいました。
そんな作品の余情に触れながらも、演者の足はこびや蹲踞の姿勢などにも注目していました。私は茶道を長く学んできましたが、いまだにすり足が苦手で、蹲踞の姿勢は1分も経つとコケてしまいます。そんなこともあり、じっくり観察した結果を今度は自分の作法に活かしていきたいと思いました。
春の休日に幽玄な世界に触れられてゆったりした気持ちになった1日でした。
🍙いばらき