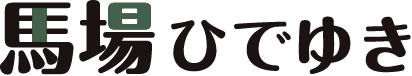連休に母を連れて、山古志の「牛の角突き」の千秋楽に行ってきました。満席のお客。そのうち1/3がリピーターとのこと。中越地震からの復興、中山間地の生活と観光のありかた、インバウンドの様子などあちこちに学ぶことがありました。
しかし一番の学びは「牛の角付き」の歴史と内容です。角付きの歴史は古く、滝沢馬琴著の「南総里見八犬伝」にその歴史についての内容が掲載されているそうです。雄牛は大事な農耕の働き手。大事な働き手を傷つけないように、戦わせても最終的には「引き分け」にしようということになったそうです。それはとても珍しいことで全国に6か所ある角付きの中でも山古志だけが国の重要無形民俗文化財に指定されています。その引き分けの瞬間も見ごたえがありました。 勢子と呼ばれる人たちが、角を突き合わせ、激しくぶつかり合う牛の間に分け入って牛を取り押さえるのです。「牛と牛の意地の張り合い、牛と人の意地の張り合い」と勢子の方の説明がありましたがその通りの迫力でした。でも闘牛が終わればノーサイドです。
約2時間かかって帰宅してテレビを付けたら、野球の日本シリーズが放映されていました。私は野球観戦が趣味ではないけれど、友人の影響もあり若いころからベイスターズが一番好きな球団。その横浜DeNAベイスターズがソフトバンクを破り26年ぶりの優勝!選手もスタンドも歓喜に沸く様子が映し出されていました。しかしそのあとソフトバンク側が敵側であるベイスターズスタンドに赴き一礼をしたのです。その際ベイスターズスタンドから割れんばかりの拍手が送られていました。野球には珍しいノーサイドの様子に私も嬉しくなり拍手をしてしまいました。
海を渡った国では、冷静さ、誠実さなどなく、お互いを完膚なきまでこき下ろすあきれた選挙戦が繰り広げられています。また勝つためには他国の兵士を前線に平気で送り、それをわかっていて兵士を送る国もあります。長年のわだかまりが解けることなく未だに互いに報復を繰り返す国々もあります。
戦いにより強いものが生き残るというのは生物の本能ではないでしょうか。そしてそれを知恵と理性を使い戦いを止め、お互いを尊重することができるのは人間だけにできる能力ではないかとも思います。山古志の牛たちは、試合中の目と試合後の目の表情がまるで異なっていました。彼らはノーサイドの意味を理解しているように思います。牛でさえ実行できること、人間が実行できないというのはどういうことなのでしょうか………。
そんなノーサイドの美学を感じた連休の一日でした。 🍙いばらき