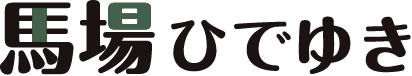事務職歴が長いせいか、いままでいろいろな会合の設営に携わってきました。その時悩むのが「席次」。テーブル席ならどの場所のテーブルが一番上席か、和室なら上座はどこかと床の間を確認から始まります。次に誰をどの席にするのかということでこれまたひと悩み。
社会人になりたての頃は、この席次で何度か失敗をして叱られました。そこで覚えたひとつのルール、それは「議員」は上座であるということ。
でもこの順位の固定観念が変わったことがありました。それは大学の地元の同窓会。諸先輩方が大勢参加されていて、中にはく首長になっている方もいらっしゃいました。私は当時事務方の手伝いをしていて、当然のように上座に議員や首長の札を置こうとしたら、先輩に「今日は同窓会。上下があるとしたら先輩後輩のみ。来賓以外はみな平等。卒業年度順に並べて」と言われたのです。なんだかその時は、その指示がかっこよく思えました。
次にちょっと立場は違いますが、弁護士組合の忘年会。高田弁護士組合ではコロナ前までは各事務所の弁護士と職員が参加して合同で忘年会をしていました。弁護士と職員が同席なんてありえないというのが一般的な感覚かもしれませんよね。しかし私が入所した頃は上座なしで弁護士も職員も全員くじ引きで席を決めていました。その効果があってかお話をした先生方とは、業務上のやり取りがしやすかったように思います。残念ながらその後弁護士席と職員席に分かれるようになってしまいました。それからは新しい先生とはお会いしても会釈程度の関係となってしまいました。その宴席の目的を考えると職種で分けるより、くじ引きの方がいいのになあと思っていました。
最近ある新年会に参加しました。そこでも上下なく参加者はランダムに席が決まっていました。なのでいつもなら上座に座る方とも席が近くなり、いろいろと貴重なお話を伺うことができました。でもひとつ気になったのが、宴席の途中で主催者が参加された議員(県議・市議)さんの名前を紹介されたのです…私は、その気遣いは不要だったのではないかと思ってしまうのですが…。どう思いますか?
🍙いばらき